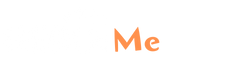【AIがないとき vs AIがあるとき】人事のためのAI活用術
「1on1を導入したけど、管理職の負担が増えるばかりで機能不全…」 「キャリア相談窓口を設置しても、申請はゼロ。本当に悩みがないの?」 「若手の離職が止まらない。彼らが本音を話してくれる場がない…」
人事担当の皆さんなら、日々痛感されていることと思います。
そして昨今は、人的資本経営が叫ばれ、個々の従業員がいかに主体的にキャリアを築き、成長していくかが、そのまま組織の競争力に直結する時代です 。
もし、社員のその「見えない悩み」や「管理職の負担」を、AIがサポートしてくれるとしたらどうでしょう?
「どうせAIでしょ?」「AIは機械的で冷たい対応だと思われない?」 そう思われるかもしれません。
しかし、もしそのAIが、「答えを教える」のではなく、「あなたの答えに寄り添う」 専門家だとしたら…?
今回は、AIキャリア相談室「HERO Me」を導入した場合の、「AIがあるとき」と、従来通りの「AIがないとき」で、人事の現場がどう変わるのか、ブログにしたいと思います。
【AIがないとき】の人事部「あるある」な日常
まずは、多くの企業が直面している「AIがないとき」の場面から見ていきましょう。
ケース1:「大丈夫です」の本音
入社3年目のAさん。最近、明らかに元気がありません。 管理職が1on1で「最近どう?」と聞いても、「大丈夫です。特に問題ありません」の一点張り。
人事が「何かあったら、いつでも相談窓口に来てね」と声をかけても、Aさんがそのドアを叩くことはありませんでした。人事にキャリアの悩みを相談することが「評価に響くのでは?」 「こんなモヤモヤを話すのは大袈裟かも」と不安に思っていたからです。
そして3ヶ月後、Aさんから人事部に「退職届」が提出されます。

【AIがないときの問題点】
- 本音の壁: 社員は「人」に相談することの心理的ハードル(評価不安、遠慮)を感じている。
- タイミングのズレ: 悩みが顕在化(退職決意)した時には、もう手遅れ
- 孤独感: 悩みを抱え込み、孤独を感じながらパフォーマンスが低下していく
ケース2:疲弊する管理職と、形骸化する1on1
B課長は、自身の業務も抱えるプレイングマネージャー。
部下の育成もミッションですが、日々の業務に追われ、1on1の「質」まで手が回りません 。
「部下のキャリア相談に乗れと言われても、自分にそんなスキルはない…」 「結局、1on1が進捗確認の場になってしまっている」結果として、部下は「管理職に話しても無駄だ」と感じ、管理職は「1on1が負担だ」と感じる悪循環に陥っています 。
【AIがないときの問題点】
- 管理職のキャパオーバー: すべての支援を「人」(上司)の力だけでカバーしようとすることに限界が来ています 。
- 支援のバラツキ: 上司のスキルや相性によって、キャリア支援の質が大きく左右されてしまいます。
ケース3:利用ほぼ0(ゼロ)の「キャリア相談室」
人事部が鳴り物入りで設置した「キャリア相談窓口」。 しかし、開設から半年、利用者は数えるほど 。
理由は明確です。 「相談担当者が人事部のCさん(兼任)だと知っているから話しにくい」 「そもそも、平日の就業時間内に相談時間を確保するのが難しい」
【AIがないときの問題点】
- アクセスの悪さ: 時間と場所の制約、そして「人」の目という制約が、利用の妨げになっています。
- 潜在ニーズの放置: 「相談するほどでもないモヤモヤ」が放置され、やがて大きな問題へと発展していきます。
【AIがあるとき】の解決策
では、「AIがないとき」のこれらの課題は、「AIがあるとき」…つまりAIキャリア相談室「HERO Me」がある世界では、どう変わるのでしょうか?
「HERO Me」は、単に相談を聞くだけのAIではありません。 最大の特徴は、「心理的資本(HERO)」 という、人が前向きに行動するための”心の原動力” に基づいて開発されている点です。
「HERO Me」は、対話を通じて相談者の思考を整理し 、相談者自身が「やってみよう」と思える具体的な一歩を見出すサポート を得意としています。

ケース1:「AIになら言える」深夜のモヤモヤが”成長”に変わる
退職するかどうしよう・・と悩み続けるAさん。 ある夜、また「仕事、向いてないかも…」というモヤモヤが襲ってきました。
Aさんは、上司や人事ではなく、スマホから「HERO Me」にアクセスします 。 「AI相手なら、評価も気にせず本音で話せる」
Aさん: 「今の仕事、自分に向いてない気がして将来が不安です」
HERO Me: 「そう感じていらっしゃるんですね。不安になるお気持ち、よくわかります。ちなみに『向いていない』と感じるのは、どんな時ですか?」
AさんはHERO Meとの対話(チャット)を通じて 、自分が「上司からのフィードバックが少なく、評価に不満を感じていること」 、そして「成長実感が持てないこと」 が不安の正体だと気づきます。
HERO MeはAさんの「自信(Efficacy)」 が低下していると判断。過去の小さな成功体験を振り返るよう促します。
対話を終えたAさんは、思考が整理され、「不安だ」と嘆くのではなく、「まずは自分の行動を可視化して、上司にフィードバックをもらいにいこう」と、前向きな次のアクション を思い描けるようになっていました。
【AIがあるときの変化】
- 24時間のセーフティネット: 「人」が対応できない時間帯や、「人」には言いにくい本音をHERO Meが受け止めます
- 内省の習慣化: HERO Meとの対話は、客観的に自分を見つめ直す「内省」のトレーニングになります。
- 「人」への橋渡し: HERO Meとの対話で思考が整理された結果、「これを上司にも話してみよう」と、次のステップ(人への相談)に進むハードルが下がります 。
ケース2:HERO Meが「1on1の予習」を手伝い、管理職の負担を激減
B課長も「HERO Me」を活用しています。 ただし、B課長が使うだけでなく、部下にも使ってもらっています 。
「次の1on1までに、HERO Meを使って『今、一番モヤモヤしていること』や『挑戦したいこと』を整理してきてくれる?その内容をベースに話そう」
部下は、HERO Me相手に自分の考えを言語化。 1on1の場では、部下は「HERO Meと話して整理できたんですが…」と、具体的なアジェンダを持って臨むようになります。
B課長の役割は、「ゼロから悩みを聞き出す」ことから、「整理された課題に対し、上司としてどう支援できるか」に集中することに変わりました 。
【AIがあるときの変化】
- 1on1の質的向上: 1on1が「進捗確認」から「未来志向の対話」の場に変わります 。
- 管理職の負担軽減: HERO Meが「思考整理」という一番時間のかかる部分を補完 。管理職は「人にしかできない判断や勇気づけ」に集中できます。
- マネジメント支援: B課長自身も、部下への接し方に悩んだ時、HERO Meに「やる気のない部下へのマネジメント」 について相談し、客観的なヒントを得ています。
ケース3:AIが「見えないSOS」を拾い、本当に必要な「人」へ繋ぐ
利用率ゼロだった相談窓口。 「AIがあるとき」の世界では、人事部が気づかないところで、HERO Meがセーフティネットとして機能しています 。
ある社員が、HERO Meに「職場の人間関係 」や「メンタルの不調 」について深刻な内容を打ち明けました。
HERO Meは対話の中で、これがAIの対話だけでは解決が難しく、「人」による専門的なサポートが必要な兆候だと判断します 。
「そのお気持ちを話してくださり、ありがとうございます。(中略)もしよろしければ、専門の相談窓口をお伝えすることも可能ですが、いかがでしょうか?」
HERO Meは、あらかじめ人事が設定しておいた社内の「人事総合窓口」や「ホットライン」 を自然な形で案内します(リファー機能) 社員は「HERO Meが勧めてくれるなら」と、人事の窓口にコンタクトを取りました。
【AIがあるときの変化】
- 潜在ニーズの掘り起こし: 「AIがないとき」には決して人事まで届かなかった「潜在的なSOS」を、HERO Meがキャッチし、適切な「人」の窓口へ誘導します 。
- 人とAIのハイブリッド支援: HERO Meが一次対応を行い、人事は「本当に人によるケアが必要なケース」にリソースを集中投下できます 。
- データの活用: 誰が相談したかは一切わかりません が、「どの時期に、どんな種類の相談(例:人間関係、キャリア不安)が多いか」という全体傾向はレポートで把握できます 。人事は、勘ではなくデータに基づいた組織改善が可能になります 。
まとめ
「AIがないとき」、私たちは社員の「個」の悩みを、人事や管理職の「人」の力だけで、なんとか支えようとしてきました 。しかし、その体制はもう限界ともいえるでしょう。
「AIがあるとき」の世界は、HERO Meが「人の弱さ(性弱説)」 を優しく補完し、人が「人にしかできない温かいケア」 や「戦略的な意思決定」に集中できる世界です。
HERO Meを「最強のサポーター」として使いこなし、より創造的で本質的な業務に時間を使うために「HERO Me」は存在します。
デモのご相談・資料請求はこちらから
まずはデモや詳細資料にて、HERO Meがをいかに活用できるのかぜひご確認ください。