
心理的資本とは?働きがいにつながる「内なるHERO」知っておきたい概要と潮流
「心理的資本」はウェルビーイング経営やワークエンゲージメント、キャリア自律に関わる要素として注目が集まりつつあります。心理的資本が重要視されている背景に触れながら、概要と動向についてまとめています。
Psychological Capital Lab
人と組織の課題の多くはマネジメントにあります。解決の糸口として、心理的資本のノウハウが活用できます。日々、様々な組織の現場と向き合っている私たちスタッフが、心理的資本研究員としてコラムやレポートで情報発信しています。
「人と組織のイキイキに効く処方箋!」として情報をお役立てください。

「心理的資本」はウェルビーイング経営やワークエンゲージメント、キャリア自律に関わる要素として注目が集まりつつあります。心理的資本が重要視されている背景に触れながら、概要と動向についてまとめています。
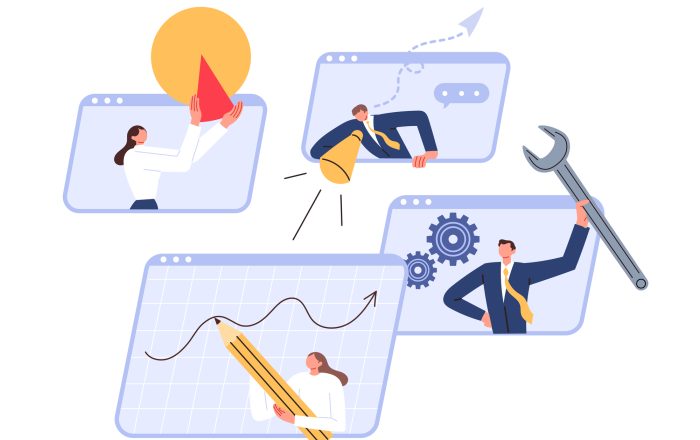
突然ですが、キャリアデザインシートを記入した経験はありますか?キャリア開発の施策の一つとして、キャリアデザインシートが多くの企業で活用されています。その有効性は認めつつも、実際に社員が一人で深く掘り下げて記入する難しさや、それをサポートする側の課題に直面することも少なくないのではないでしょうか。「もっと、社員一人ひとりに寄り添った支援ができないか?」 「限られたリソースの中で、どうすればより質
Copyright © Be & Do Inc.