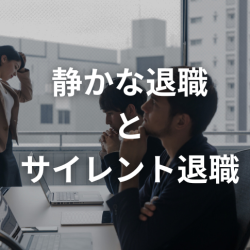先日、横浜市立大学と神奈川大学の研究グループが、従業員が設定された目標の難易度と「ワーク・エンゲージメント(働きがいや、やりがい。仕事に対する前向きな熱意や、活力そのものを指す)」の関係を「心理的資本」が強化することを発見したという研究が発表されました。合わせて、その研究の中では勤続年数の長い従業員では、目標難易度とワーク・エンゲージメントの関係が弱くなることが見られたとのことでした。
論文情報:【European Accounting Review】Target Difficulty, Psychological Capital, and Work Engagement
この研究は、目標の難易度が従業員の仕事への熱意(ワーク・エンゲージメント)に与える影響を、心理的資本(PsyCap)がどのように調整するかを検証したもので、具体的には、日本の上場企業に勤務する1,404名の従業員を対象に調査を行い、以下のことが明らかになりました。
- 目標の難易度が高いほど、従業員のワークエンゲージメントは高まる傾向がある。
- 心理的資本(自己効力感、楽観性、希望、レジリエンス)が高い従業員ほど、目標の難易度とワークエンゲージメントの間の正の関係が強くなる。
この研究は、目標設定理論に基づき、心理的資本が目標の難易度とワーク・エンゲージメントの関係に与える影響を実証的に示したものと言えます。これらは経営管理会計研究、特に心理学的視点が用いられています。
ガイディング(心理的資本を高める方法)視点でのレビュー
心理的資本を構成する4つの要素(Hope、Efficacy、Resilience、Opitimism)が高い状態は、どれだけ高い厳しい目標であっても仕事に対してポジティブに向き合うことができることは、とても納得のいく話です。
高い目標であっても、そこに向かうための経路となる方策をいくつも思い描くことができ、一歩ずつ前に前進するための適切な中間目標となる目標設定もできる状態だからです。これはHope(意志と経路の力/希望)が高いからできることです。
また困難な目標であっても「自分にもできそうだ」「自分にならやれる」という自信があれば、その場でまごつくことなく小さくとも確実に行動を起こすことができるでしょう。これはEfficacy(自信と信頼の力/効力感)で説明できます。
そして困難な目標に向かうことをピンチではなくチャンスと捉えることができる状態というのは、Resilience(乗り越える力/超回復力)で説明できます。リスクを適切に捉え、自らの考え得る資産や資源を自己認識できていて、それらを活用して課題を乗り越える準備ができているでしょう。
さらに、どのような状況であっても、自分にできることをしっかりやりきろうとするし、たとえ容易にうまくいかなかったとしても、その経験を資産に変えて次に向かうことができるOpitimism(現実的で柔軟な楽観力/楽観性)を持ち合わせていることは間違いないでしょう。
こうしたことをセルフコントロールできる状態だとすれば、それはまさしく心理的資本が高い状態と言えます。
今回の研究で興味深いのは「勤続年数」によって目標難易度がエンゲージメントに作用しなくなるという点です。
どんな目標を設定しているかによると思うのですが、おそらく同じ業務における目標の場合は慣れが生じてきているのだという仮説を立てることができます。または「これくらいやれば、これくらいの評価を得られる」という組織風土への慣れのようなものも考えられるでしょう。
目標の難易度だけではなく、携わる業務の幅を拡げたり、全く新しい挑戦を促すなど「領域(ドメイン)」を拡げるような機会づくりや、「良い緊張感」を持てるような機会づくりを企業も個人も双方で意識していかないと、現状に満足をしてしまい刺激が足りなくなるのでしょう。
ガイディングにおいて心理的資本、特にそのうちEfficacy(自信と信頼の力/効力感)を高めるということを考える時には「成長に限界はない」という捉え方を前提とします。
勝手な推測ですが、この調査で「勤続年数」によって目標の難易度に関わらず、働きがいや活力の向上には関係が弱くなるという場合は、その従業員の方々自身が「自分で限界を決めている」か「現状に満足している」という可能性が高いのでは?と推測します。
こちらの記事も参考に。
さいごに
なぜ目標が高くても前向きに動ける人と、動けない人がいるのかということの要因の一端が分かる研究論文でした。
心理的資本が高いと目標達成意欲が高く、前向きに行動ができるということの証明につながるのではいでしょうか。改めて調査結果を発表いただきありがとうございます。
ではその心理的資本をどう高めていくと良いのか。
その高め方、高めるための思考法や手法を体系的に学習し、知識・スキルとして身につけること。それができるというのが「心理的資本は開発できる」という所以だと思います。
株式会社Be&Doでは、心理的資本を高める方法を学び、心理的資本開発指導士を養成する「PsyCapMaster®認定講座」を開講しています。ぜひ受講をご検討くださいませ。
また心理的資本を開発する思考整理や目標設定をアシストするという特徴を持つ「AIキャリア相談室HERO Me(ヒロミー)」も、お問合せくださいませ。